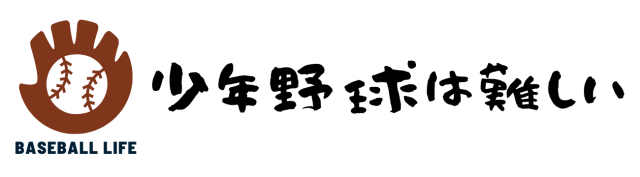バッティングで一番大事なのは“タイミング”。理屈より、動から動。

この記事の内容は科学的根拠に基づくものではありません。
あくまで筆者の主観と、少年野球の現場での経験をもとに書いたものです。
すべての子どもに当てはまるものではなく、
「こういう考え方もあるんだな」くらいの気持ちで読んでもらえると嬉しいです。
長年グラウンドで子どもたちを見てきて思う。
「打てる子」と「打てない子」には、明確な共通点がある。
フォームが悪いわけでもない。
真面目に練習してるのに、試合になると結果が出ない。
そういう子を何人も見てきた。
最初は道具やスイングの問題かと思っていたけど、
気づいたら“構え”や“心の状態”のほうにヒントが隠れていた。
構えた瞬間、
「この子は打ちそうだな」「今日は苦戦しそうだな」
正直、だいたい分かる。
打てない子には、共通のサインがある。
力み、硬さ、焦り。
その空気は、バットを振る前から漂ってる。
この記事では、
現場で感じた「打てない子の共通点」と、
そこから見えてきた“改善のヒント”を紹介する。
打てない子の共通点
- バットのサイズが合っていない
- 力みすぎて体が動かない
- 頭が動きすぎてボールを見失う
- “静”から“動”になっている
- 空振りを怖がって当てにいく
バットのサイズが合っていない
意外と多いのが、バットのサイズ問題。
「ちょっと重い方が力がつく」と言って、
身長に対して長すぎ・重すぎるバットを使っているケース。
結果、スイングが遅れてボールに差し込まれる。
そして「当てられない」→「怖い」→「力む」の悪循環。
まずは“軽くて振り切れるバット”を選ぶこと。
子どもが自然に振れる重さで、
「振るのが楽しい」と思えることが第一歩だ。
力みすぎ
“打とう”と意識するほど、構えの段階で固くなる。
肩も腕もギュッと力が入り、スイングが遅れる。
打てる子の構えは柔らかい。
バットを「構える」というより、「置いてる」。
余裕のある姿勢が、いいリズムを生む。
「構えたときに息してる?」
たまにそう聞くと、力んでる子ほど笑って気が抜ける。
それでスイングが一気に変わることも多い。
頭が動きすぎ
ピッチャーの球を“追いかけすぎて”頭が前に突っ込む。
ボールを見てるようで、実は見えていない。
頭が動けば、目線がズレる。
タイミングも崩れる。
大事なのは「顔を残す」より「地面を踏む」。
足で我慢すれば、自然と頭は動かない。
「地面をグッと押す感覚」を覚えるだけで、
スイングの安定感は格段に変わる。
“静”から“動”になっている
止まった構えから急に動こうとする子は、
ピッチャーに出遅れる。
バッティングは「静から動」ではなく「動から動」。
構えながら小さくリズムを取る。
ピッチャーの動きに合わせて体を揺らすくらいがちょうどいい。
止まってると、いつも“置いてかれる側”になる。
ほんの小さな揺れが、
「タイミングを取るセンス」を育ててくれる。
空振りを怖がって当てにいく
三振を怖がる子ほど、バットを“出すだけ”になる。
ボールに触ることが目的になってしまう。
でもピッチャーからすれば、
当てにくるバッターなんて全然怖くない。
小学生のうちは、空振りでいい。
とにかく“強く振る”ことを覚える。
強く振る中で、スイングの形やタイミングは自然と身につく。
空振りを恐れない子は、
自分のスイングを信じられる子だ。
鬼コーチ流 改善アプローチ
打ちたいという気持ちは大事。
でも、それが強すぎて力が入りすぎると本末転倒。
子どもにはよく言う。
「力を出すには、まず力を抜け。」
たとえば垂直跳びをやらせると分かりやすい。
子どもは飛ぶ直前、必ず一瞬“ふっ”と力を抜く。
力を出すためには、力を入れる前に抜く瞬間が必要なんだ。
バッティングも同じ。
打ちにいく直前に一度、力を抜ける子は強いスイングができる。
でも、構えの時点でがちがちに力が入ってる子が
その瞬間だけ力を抜けることなんて、まずない。
だから、最初に直すべきは構え。
“リラックスして動ける構え”を作ることがすべての出発点だ。
トップで力を抜く意識
勘違いしてほしくないのは、
構えで力が入ってること自体が悪いわけじゃない。
構えにある程度の緊張感は必要。
問題は、トップのタイミングで力を抜けないこと。
ピッチャーの動きに合わせてトップに入る瞬間に、
ほんの一瞬でも“脱力”できると、
スイング全体の流れが一気にスムーズになる。
トップががちがちになると、
体もバットも遅れる。
いわゆる「差し込まれる」ってやつだ。
力を抜ける子は、タイミングが合いやすい。
だから構えもトップも“動ける柔らかさ”が大事になる。
動き続けるバッターは強い
とにかく大事なのは、“止まらないこと”。
新庄監督が現役時代に言っていた。
「バッターボックスでは歩くようなイメージで構えていた」
まさにその通り。
リズムを止めず、常に“動から動”。
足でリズムを取る。
腕でリズムを取る。
体を揺らしてリズムを取る。
方法はなんでもいい。
自分に合った形でいいから、
とにかく動きを止めないでほしい。
その感覚をつかむのにおすすめなのがこれ👇
- 2〜3歩歩いてから素振りをする
- 置きティーで2〜3歩歩いて打つ
今でも子供にはやらせている。
歩きながらのスイングで、
自然と体の連動やタイミングの“抜きどころ”が身につく。
結局のところ…
縦振り、ステイバック、ドアスイング、間の作り方――
技術的な言葉はいくらでも出てくる。
でも、小学生のうちはそんなことより
まずリラックス・動から動・強いスイング。
それができて初めて、次の技術(ワンランク上の理論)に進める。
小学生にとっての“上達”は、
「うまく当てる」ことじゃなくて、
「気持ちよく振れる」こと。
それができるようになった子は、
必ず打てるようになる。
鬼コーチの結論
打てない子の共通点は、
技術よりも“心と体の動かし方”にある。
構えで固くなり、タイミングを外し、
空振りを恐れて力を抜けない――
そんな姿を何度も見てきた。
結局、野球が上手くなるかどうかは、
技術よりも気持ちの柔らかさ。
「失敗してもいい」と思えた瞬間に、
構えもスイングも一気に変わる。
もちろん技術も大事だ。
明らかにおかしい癖がついているなら動画を撮って
子供に見せて納得させてから一緒に改善していくことも必要。
でも最近はYouTubeやSNSで、
たくさんの野球理論や練習法が簡単に手に入る時代。
でも、それが自分の子どもに本当に合っているかを
見極めるのは親や指導者の役目だと思う。
メジャーリーガーの理論を小学生に当てはめる必要はない。
画面の中の選手を真似する前に、
目の前の子どもをよく見てあげてほしい。
体格も性格も違う。
その子の「今」に合わせた言葉と練習を選んであげること。
それがいちばんの指導だと思う。
合わない理論でつぶれた子も見てきた。
でも、子どもをちゃんと見てあげる大人がいれば、
その子は必ずもう一度立ち上がれる。
グラウンドから綴る Written on the Field
鬼コーチ
子どもたちには厳しいけれど、本気で成長を願っている「鬼コーチ」です。 怒るのは、技術じゃなく“心”の部分。 教えているつもりが、いつも子どもたちに教えられています。