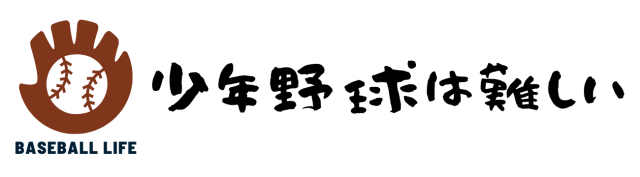チーム選びで失敗しないために|親が見るべき“指導方針”とは何か

少年野球のチーム選び。
これは親にとって、思っている以上に難しい。
子どもが楽しめるか、指導者との相性、保護者の関わり方──
どれかひとつでもズレれば、せっかくの野球がストレスになってしまう。
自分の経験を通して感じたのは、「チーム選び=親の覚悟」だということ。
この記事では、実際に少年野球チームでコーチを務める立場から、
チーム選びで後悔しないために大切なポイントを話していきたい。
きっかけは「お茶当番なし」だった
長男が少年野球を始めたのは小学3年の夏。
本当は1年生の頃からやらせたかった。
ただ、当時はまだ「少年野球=母親の当番必須」というイメージが根強かった。
嫁さんは土日仕事。
「お茶当番ができないなら無理だろう」と、ずっと諦めていた。
そんな中、ふと小学校で配られたチラシに目がとまった。
「お茶当番なし」──たった一言だったけど、その瞬間にすべてが変わった。
「これならいけるかもしれない」と、すぐ体験に行き、その日のうちに入団を決めた。
息子自身は最初、それほど乗り気ではなかった。
友達に誘われていった程度だったが、グラウンドでボールを追いかけるうちに少しずつ変わっていった。
初めて打球を捕った瞬間の笑顔、声を掛け合う楽しさ──。
あっという間に「次の練習、まだ?」と言うようになった。
親の思い込みで止めていた時間が、一気に動き出した気がした。
想像していた「少年野球」とは違った
正直、最初は驚いた。
自分が子どもの頃は、監督の怒鳴り声、叩かれるのは当たり前。
泣いても練習を続け、仲間と一緒に“根性”で強くなる──それが少年野球だった。
けれど、今のチームはまるで別世界だった。
監督はとにかく穏やかで、怒鳴らない。
子どもたちものびのびと声を出し、笑顔が絶えない。
練習の合間にも笑い声が聞こえて、みんなが“楽しそう”に野球をしている。
最初は正直、拍子抜けした。
「これで強くなれるのか?」と。
でも、それが現代の少年野球なんだと思うようになった。
子どもたちは本当に仲が良く、下の学年の子にも優しい。
負けても責めることはなく、勝てばみんなでハイタッチ。
このチームに入ってから、息子の性格も少しずつ変わった。
素直になり、家でもチームメイトの話ばかり。
「このチームでよかった」──心からそう思えるようになった。
チーム選びで大事なのは“指導方針”
少年野球チームはどこも同じように見えるが、実際はまるで違う。
指導者が何を一番大切にしているかで、チームの雰囲気も、子どもの成長の形も変わる。
うちの監督は、**「全員出場」**を徹底している。
どんな大会でも、どんな相手でも、必ず全員を出す。
結果、エラーで負けることもある。
それでも監督は決して責めない。
「次があるから」と言い、子どもたちを励ます。
この姿勢には頭が下がる。
ただ、時にモヤモヤすることもある。
本気で努力している子、誰より練習している子が、試合に出ても報われない瞬間がある。
逆に、普段あまり真面目にやらない子が平等に出場する。
そのたびに、**「平等と公平の違い」**を考えさせられる。
勝つことを目指すのが悪いわけじゃない。
でも、勝つために努力する姿勢を見せることを、もっと大切にしてもいいと思う。
“勝ちにこだわる”という言葉は、ただの結果主義じゃない。
子どもが本気で向き合うきっかけでもある。
体験や雰囲気だけでは分からない
体験や見学は、どこのチームも明るい雰囲気だ。
コーチは優しく、子どもたちも笑顔で迎えてくれる。
けれど、それはほんの一部。
実際に入ってからでないと分からないことが山ほどある。
- 怒鳴るコーチが一人いるだけで空気が変わる
- 保護者同士の派閥ができていて、居づらくなる
- 「お茶当番なし」と言いながら、実際は裏で当番制が回っている
こうしたことは、パンフレットにも体験会にも出てこない。
結局のところ、**「人」**でチームの雰囲気は決まる。
監督やコーチの性格、保護者の考え方、子どもたちの関係性──
この3つのバランスが崩れると、どんなに良いチームでも続かなくなる。
だから、チーム選びで一番大事なのは「方針」だけじゃない。
“空気”を見抜く力。
そして、その空気が自分たち親子に合うかどうか。
鬼コーチとして思う“いいチーム”とは
いいチームって、勝つチームでも、優しいチームでもない。
**「子どもが家に帰ってどんな顔をしているか」**で決まると思っている。
怒られて泣くことがあっても、翌日も野球に行きたがるなら、それは良いチーム。
負けて悔し涙を流す子がいるチームは、必ず強くなる。
そして、監督やコーチが全員を本気で見ているかどうか。
ここが一番大きい。
できる子だけを可愛がるチームは、最初は強いけれどすぐ崩れる。
反対に、全員を平等に育てようとするチームは、時間はかかっても必ず伸びる。
指導方針に正解はない。
ただ、「子どもを本気で見てくれる大人がいるか」──
それだけは、どのチームにも共通する“良いチーム”の条件だと思う。
チームの“方針”が子どもを伸ばす
少年野球は、単なるスポーツじゃない。
子どもだけでなく、親も一緒に成長する場だ。
だからこそ、チーム選びは「誰と関わるか」を選ぶことでもある。
監督の性格が合わなくても、指導方針に一貫性があれば子どもは伸びる。
逆に、どんなに優しいチームでも、方針がブレていると子どもは迷う。
最後に見るべきは、練習中の子どもたちの表情。
そこに“本音”がある。
笑顔の中にも本気があるチーム。
悔し涙のあとにまた笑えるチーム。
そういう場所を選べば、間違いはない。
チームを決めたあとに待っているのは、“大人同士”の関係性。
そこに潜む落とし穴について書いたのがこちら。
グラウンドから綴る Written on the Field
鬼コーチ
子どもたちには厳しいけれど、本気で成長を願っている「鬼コーチ」です。 怒るのは、技術じゃなく“心”の部分。 教えているつもりが、いつも子どもたちに教えられています。