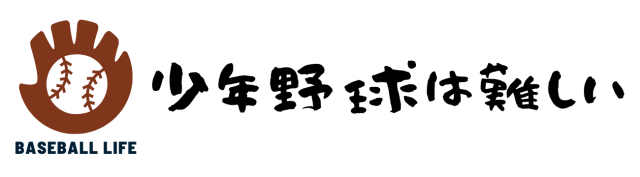エラーする子の共通点。足が止まった瞬間、守備は終わってる。

この記事の内容は科学的根拠に基づくものではありません。
あくまで筆者の主観と、少年野球の現場での経験をもとに書いたものです。
すべての子どもに当てはまるものではなく、
「こういう考え方もあるんだな」くらいの気持ちで読んでもらえると嬉しいです。
長年少年野球の現場で子どもたちを見てきて、
“エラーをする子”には明確な共通点がある。
守備のうまい・下手は、
正直センスや才能じゃない。
動ける準備ができてるかどうか。
それだけで大きく差がつく。
どんなに上手い子でも、
足が止まった瞬間に守備は終わっている。
エラーする子の共通点
- 足が止まる
- ボールの正面でボールを見る
- グラブの位置が高い
- 真面目すぎる
- 基礎練習が足りない
足が止まる
「足が止まってるぞ!」って練習中によく言うけど、
その意味をちゃんと理解してる子は少ない。
足が止まるってのは、
“最初の一歩が遅い”ことじゃない。
捕球の瞬間に足が動かなくなることを言う。
打球によっては、もちろんその場で待つ判断もある。
それ自体は悪くない。
でも、捕球のタイミングでリズムを取れずに
ピタッと止まってしまうと、
グラブも体も硬くなってミスにつながる。
守備はリズム。
捕球の瞬間に足が動いていると、
自然と上半身の力も抜けて、スムーズに次の動作に入れる。
“動きながら捕る”っていうのは、
ずっと走り回るって意味じゃない。
最後の一歩までリズムを保つこと。
これができる子は、打球の強さにもタイミングにも対応できる。
ボールの正面でボールを見る
守備でよく言われる「ボールの正面に入れ」。
でもこれ、受け取り方を間違えると逆効果になる。
多くの子は“ボールの正面で待ってしまう”。
すると、打球が自分に向かってくるから怖い。
顔が上がって、グラブが遅れて、結果エラー。
正面ってのは、“待つ場所”じゃない。
入りながら作るもの。
ボールは、左手(グラブ)のラインに入れて目で追う。
顔でボールを追うとブレる。
左手の延長線上にボールを入れるイメージで。
そして、捕球の瞬間に左足を出しながら正面に入る。
これで自然に“動きながら捕る”形になる。
構えた位置で止まって待ってたら、
どんな上手い子でも怖くて動けない。
だけど、自分から入っていけば、
打球が“迎えに行く相手”になる。
グラブの位置が高い
構えたとき、グラブが胸の高さにある子は、
ほとんどの打球に反応が遅れる。
内野の打球は下から来る。
だから最初からグラブは“下に置いておく”。
低い構えから高い打球は取れるけど、
高い構えから低い打球には間に合わない。
最初から“下に構える癖”をつけるだけで、
エラーは劇的に減る。
真面目すぎる
一見、守備が上達しそうに見えるタイプ。
「腰を落として」「正面で捕って」
そういう基本を忠実に守ろうとする。
でも、試合になると――
足が止まる。
バウンドに合わないのに動けない。
いい意味での“適当さ”がない。
野球の守備は採点競技じゃない。
フォームがきれいでも、アウトが取れなきゃ意味がない。
もちろん“股割っての基礎”はものすごく大事。
だけど、それもアウトにするためのひとつの手段にすぎない。
場合によっては、
思い切って前に出てシングルキャッチでいい。
間に合わなそうなら逆シングルでさばいてもいい。
ときにはジャンピングスローだって構わない。
大事なのは、柔軟に動けるかどうか。
真面目すぎる子ほど「こうしなきゃ」に縛られて動けなくなる。
正解にこだわりすぎて“結果”を逃す。
守備で一番強いのは、
状況に合わせて体が勝手に反応できる子。
頭で考えすぎず、動きながら答えを出せる子。
だからこそ、普段の練習でも
「完璧に捕る」じゃなく「どうすればアウトにできるか」
を意識してほしい。
基礎練習が足りない
これはもうシンプルに。
キャッチボール、ゴロ取り――
当たり前の練習を“作業”でやる子は、
いつまでたっても守備が安定しない。
守備が上達しない子は速い打球のノックや
難しいノックをやりたがる。
基本ができていないのにそんなことしても下手になるだけ。
捕る、投げる、構える。
この「地味な繰り返し」の中に
守備の感覚が全部詰まってる。
1日10分でもいい。
“ちゃんと捕る”という時間を増やすだけで、
守備は変わる。
鬼コーチ流 改善アプローチ
「止まらない捕球」を身につける
守備の基本はリズム。
捕球の瞬間に足がピタッと止まったら、
どんな上手い子でもミスをする。
練習のときは、
捕球の直前に足を動かす意識を持たせる。
1、2、3でステップを踏んで捕るとか、
テンポを声に出しながらやるのもいい。
捕球しながらステップを切る。
「足で捕る」っていう感覚を体に染み込ませる。
これだけで守備が一気に軽くなる。
「正面に入る」は“動きながら作る”
正面に入ること自体は大事。
でも「正面で待つ」のは違う。
打球に向かっていく途中で
左足を出しながら正面を作る。
これが理想的な入り方。
まずは簡単ゴロからボールを追う際のラインの確認から。
ほとんどの子は真正面のラインでボールを追っていく。
簡単なゴロならいいがこれが打球が速くなると
怖くて逃げる。
だからゴロ捕球からボールのラインの入り方を覚えさえることが大事だ。
グラブは“下から上”
簡単そうでこれが意外にくせ者。
特に逆シングルは虫取りばっかり。
簡単なゴロ捕球を左右に振ってグローブが膝より下の位置のまま
ボールを追ってそのまま捕球。
これを繰り返すことによってグローブを低くの感覚が身に付く。
“真面目さ”をリセットする練習
「腰を落として」「正面で捕って」
そればっかり意識してる子は、動きが硬い。
そんな子には、あえて自由な捕り方の練習をさせる。
逆シングル、片手キャッチ、ジャンピングスロー。
失敗してもいい。
守備は採点競技じゃない。
どんな形でもアウトにできたら“正解”。
その感覚をつかむことで、
「完璧じゃなくてもいいんだ」という柔軟さが出てくる。
結局のところ
内野守備は、
上手い子ほど「動いてる」。
下手な子ほど「止まってる」。
力を抜いて、リズムを持って、前へ出る。
そして何より――
アウトにするためにどう動くかを考える。
それが鬼コーチ流の守備。
フォームじゃなく“動き”で見せる守備。
鬼コーチの結論
内野守備は、技術よりもリズム。
足を止めず、力を抜いて、動きながら捕る。
それだけで守備の質は一気に変わる。
うまい子はみんな、捕球の瞬間まで動いている。
リズムがある。
“正面に入る”ことを形で覚えていない。
動きながら正面を作っている。
そして何より大事なのは、柔軟さ。
「腰を落として」「正面で」と教わった基本を
100%守ることが“正解”じゃない。
アウトを取るために、時には崩していい。
守備は採点競技じゃない。
捕れたかどうか、アウトにできたかどうか。
そこにすべてがある。
守備で大事なのは「綺麗さ」より「対応力」。
シングルでも、逆シングルでも、ジャンピングスローでもいい。
自分の動きでアウトにできるかが全てだ。
だからこそ、放課後に野球して遊んでる子は強い。
友だち同士で砂ぼこりまみれになって、
捕って投げて転んで笑って――そういう中で、
“動きながら捕る”ことを自然と覚えている。
野球塾だけで真面目に練習してる子は、
どうしても“自由な発想”が出にくい。
野球は「正解を覚えるスポーツ」じゃない。
自分で動いて、自分で掴むスポーツ。
遊びの中で身につく「動きの感覚」「タイミング」「怖がらない心」――
それが結局、守備力になる。
と俺は思う。
グラウンドから綴る Written on the Field
鬼コーチ
子どもたちには厳しいけれど、本気で成長を願っている「鬼コーチ」です。 怒るのは、技術じゃなく“心”の部分。 教えているつもりが、いつも子どもたちに教えられています。