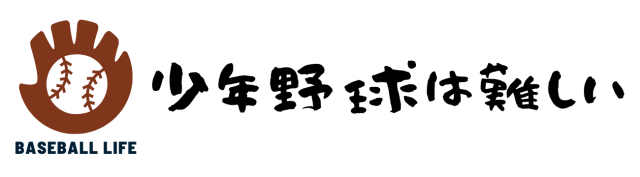レギュラーの選び方でチームは壊れる|鬼コーチが語る選定基準

少年野球で一番揉めるのが「レギュラーの選び方」だ。
親も子どもも敏感で、指導者にとっては頭の痛いテーマ。
「なぜあの子が出て、うちの子は出ないのか」
そういう声が、チームを静かに壊していく。
俺も何度もその渦の中にいた。
仲間を信じられなくなる空気、試合のたびに変わる視線。
だからこそ、はっきり言いたい。
レギュラーの選び方に“正解”なんてない。
けれど、**「軸」**を持たないチームは必ず崩れる。
今回は、俺なりの“選定基準”を正直に話したい。
そもそも争えるほど人数がいない
正直に言うと、
少年野球の多くのチームは「レギュラー争い」なんてものが成立していない。
人数がギリギリ。
試合を回すのに精一杯。
だから、良くも悪くも“ぬるい”状態になってしまう。
「誰を出すか」より、「誰を出さないと試合ができないか」。
そういう発想でメンバーを決めるチームがほとんどだ。
でも、だからこそ怖い。
人数が少ないチームこそ、「甘え」や「馴れ合い」が生まれやすい。
試合に出られて当たり前。
レギュラーという言葉の意味が、どんどん薄れていく。
俺のチームも、例外じゃない。
“レギュラー争い”なんてほど遠い。
でもその分、
ポジションや打順の決め方一つで、子どもたちのモチベーションが大きく変わる。
だから俺は、そこを一番大事にしている。
毎年変わる“方針”と“価値観”
うちのチームでは、毎年ヘッドコーチが交代する。
6年生の親がヘッドコーチになる仕組みだ。
このやり方の良いところは、みんながチーム運営に関わる意識を持てること。
でも、悪いところは──方針が毎年変わること。
ある年は「結果重視」。
次の年は「全員出場」。
その次の年は「楽しむこと優先」。
子どもたちは大人の方針に振り回され、
何を目指せばいいのか分からなくなる。
監督は、良くも悪くも“人の意見をよく聞く”タイプ。
だからこそ、ヘッドコーチの性格や考え方によって
チームの色が大きく変わる。
去年は「上手い子中心」だったのに、
今年は「6年生優先」。
その変化に、子どもたちは戸惑う。
「どうせ何やっても出られない」と感じた子の目の輝きが、
少しずつ消えていくのを俺は何度も見てきた。
勝つために、上手い子を出す
俺の考えはシンプルだ。
勝つために、学年関係なく上手い子を出す。
「うまい子を出す」と言うと冷たく聞こえるかもしれないが、
それがチームを強くし、結果的に子どもたちの成長につながる。
ただし条件がある。
練習に真剣に取り組むこと。
チームに貢献しようとする姿勢があること。
この2つを満たしていなければ、どんなに上手くても出さない。
けど実際のところ、
「練習を適当にやってるのに上手い子」なんてほとんどいない。
練習に真面目な子が上手くなる。
単純だけど、それが現実だ。
努力と上達は、ほぼ比例する。
だから、俺の中では“基準”は自然と明確になっている。
試合に出す子は、「日々の姿勢で信頼できる子」。
それだけ。
それでも、納得できない瞬間がある
とはいえ、理屈では割り切れない現実もある。
たとえば──
5年生がやる気もなく、下手で、声も出ない。
でも、「上の学年だから」「6年生が少ないから」という理由で
その子が試合に出る。
その一方で、4年生の中には誰よりも声を出して、
練習に真剣に取り組んでいる子がいる。
それでも試合に出られない。
そういうとき、俺は心の中で何度も「違うだろ」と叫んでいる。
“努力が報われない”チームほど、
子どもたちのやる気を奪うものはない。
それはただの「学年優先」じゃなく、
子どもの心を折る“指導者の逃げ”だと思う。
「チームのため」をどう捉えるか
もちろん、試合に出る・出ないだけで全てが決まるわけじゃない。
ベンチにいても声を出してチームを支える子がいる。
そんな子も本気でチームを背負っている。
でも、指導者が“出す子”を選ぶ基準を持っていなければ、
子どもたちはその努力を「無意味」だと感じてしまう。
それが一番怖い。
「チームのために頑張る」っていう言葉は、
“公平な基準”があって初めて成立するものだ。
指導者がそこをあいまいにした瞬間、
チームは一気に崩れる。
レギュラーは“評価”じゃなく“責任”
レギュラーっていうのは、単なる“評価”じゃない。
チームを引っ張る責任のポジションだと思っている。
ベンチにいる子の想いを背負って、
グラウンドに立つ覚悟が必要だ。
だから俺は、
“うまい子”より“本気でチームを強くしたい子”を選びたい。
たとえ小さな声でも、真っすぐ届く声を出せる子。
そういう子を、俺は試合に出したい。
レギュラーの選び方で、チームは本当に変わる。
基準をあいまいにした瞬間に、チームは壊れる。
それだけは、これから先も絶対に忘れたくない。
「勝たせたい」と「育てたい」の狭間で揺れるのは、どの指導者も同じだと思う。
その葛藤を書いた記事がこちら。
グラウンドから綴る Written on the Field
鬼コーチ
子どもたちには厳しいけれど、本気で成長を願っている「鬼コーチ」です。 怒るのは、技術じゃなく“心”の部分。 教えているつもりが、いつも子どもたちに教えられています。