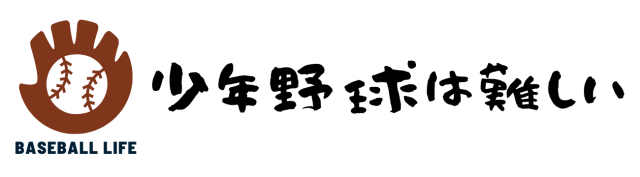俺は複合バット反対派。|「飛ぶバット」が奪うもの、育てるもの

最近の少年野球を見ていて、どうしても引っかかることがある。
それは——バットだ。
ウレタンやカーボンの複合バットが当たり前になり、
軽く当てただけで外野の頭を越える。
芯を外してもヒットになる。
まるで“道具が野球をやっている”ような感覚さえある。
「飛ぶから楽しい」「結果が出るから自信になる」
そう言う親も多い。
たしかに、それも間違いじゃない。
打てなければ野球はつまらないし、結果が出る喜びは子どもを動かす。
でも——現場で見ていると、どうしても違和感がある。
その「飛ぶバット」で生まれたヒットに、
“努力の手ごたえ”はあるのか?
当てれば飛ぶ。
努力しなくても結果が出る。
それって、本当に子どもたちのためになっているのか。
俺は、複合バット反対派だ。
そしてその理由は、“飛ばない悔しさ”の中にこそ、
野球の本当の面白さがあると思っているからだ。
俺は“複合バット反対派”
うちのチームにも、複合バットを使う子は多い。
ウレタン素材のものもあれば、カーボン製の軽量タイプもある。
ウレタンほどではないにせよ、どちらも“飛ぶ”。
そして下の子は木製バットを使っている。
飛ばないけれど、芯で捉えたときの感触を覚えてほしい。
“本物の手ごたえ”というやつだ。
俺は、普段から自主練をして、基本がしっかりできている子が使うならいいと思っている。
フォームが安定していて、自分のスイングを理解している子。
そういう子なら、道具を“活かせる”。
でも、まだ基礎もできていない子が使うと、ただの“魔法の棒”だ。
結果だけが先に出て、技術の積み重ねがない。
「打てた」「飛んだ」で終わってしまう。
投手目線で見ると、ひどいもんだ
俺はピッチャー出身だから、余計に思う。
複合バットは、投手の努力を無にする道具だ。
根っこで詰まらせた打球が外野まで飛ぶ。
力のある大きな子がちょんっと当てただけで外野オーバー。
投げる側からすれば、理不尽でしかない。
投手の肘を守るために球数制限をしているのに、
バッターの飛距離は道具の力でどんどん伸びていく。
これじゃ本末転倒だ。
うちのチームにもいる、“バットに振られてる子”
うちのチームにもいる。
まだスイングすらまともにできないのに、
4万、5万もする高価な複合バットを持っている子が。
「飛ぶバットなら打てるようになる」と信じる親の気持ちも分かる。
けれど現実は逆だ。
打てない。飛ばない。
そりゃそうだ。
基本もできてない。振る力もない。
しかもサイズが合っていない。
長くて重い“飛ぶバット”を無理して構えている。
結果、フォームは崩れ、スイングは遅くなり、
“振り切る感覚”を身につける前に終わる。
それでも親は言う。
「高いバットなのに、なんで打てないの?」
子どもは苦しむ。
悪循環だ。
指導者としてのジレンマ
正直、俺だって子どもに「そのバットじゃ無理だ」とは言いにくい。
せっかく親が買ってくれたものを否定するようで。
でも、本音を言えばこうだ。
まずは自分に合ったバットで振り込め。
芯で捉えた感触を体で覚えろ。
打球が飛ばなくても、それが“上手くなる途中”だ。
技術を積み上げる過程を、道具が奪ってはいけない。
複合バットが奪っているもの
複合バットの問題は、
“飛ぶ”ことそのものよりも、
「考えなくても結果が出る」構造にある。
・なぜ打てなかったのか
・どうすれば強い打球が打てるのか
・どこで捉えれば一番飛ぶのか
本来、子どもたちは失敗の中でこういうことを学んでいく。
でも、道具が勝手に結果を出してくれると、
その“考える時間”がなくなる。
技術よりも「打てた・飛んだ」が評価される。
でも、それは本当の成長じゃない。
それでも完全否定はしない
矛盾して聞こえるかもしれないけど、俺は複合バットを完全否定はしない。
あの打球を見て笑顔になる子どもたちを見ると、
やっぱり「野球って楽しいな」と感じる。
その笑顔が、野球を続ける原動力になることもある。
だから“入口”としての複合バットはありだと思う。
けれど、“続ける”なら、いつか壁にぶつかる。
そのときに必要なのは、
バットの性能じゃなくて、自分の力だ。
俺の願い——金属と木製だけの時代に戻ってほしい
でも正直なところ俺は願っている。
金属と木製だけの時代に戻ってほしい。
飛ばないからこそ、努力する。
努力するからこそ、打球が飛ぶ。
その「手ごたえ」が、子どもたちを成長させる。
複合バットが“飛ばす”のはボールだけ。
でも俺たちが育てたいのは、“自分の力で掴む喜び”だ。
バットが飛ばすよりも、気持ちが届く野球を。
そういう野球を、俺はこれからも子どもたちに教えていきたい。
「道具」よりも大切なのは“気持ち”だと改めて思う。
そんなことを痛感したあの日の話を。
グラウンドから綴る Written on the Field
鬼コーチ
子どもたちには厳しいけれど、本気で成長を願っている「鬼コーチ」です。 怒るのは、技術じゃなく“心”の部分。 教えているつもりが、いつも子どもたちに教えられています。