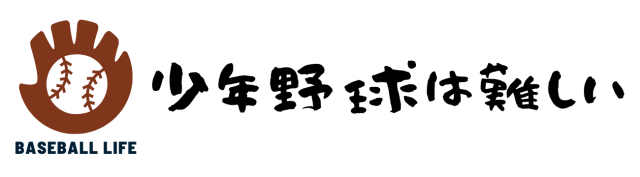「楽しい野球」って一体なんだ。本気でやるからこそ笑顔は輝く。

少年野球ではよく聞く言葉がある。
「楽しくやろう」「笑顔でプレーしよう」。
けれど、その“楽しい”は、本当に子どもたちの成長につながっているのか。
最近の子どもたちを見ていると、どこか“楽しい”を履き違えている気がする。
ふざけることが楽しさになり、本気を出さなくても許される空気。
だけど俺は思う。
本気でやるからこそ、心の底から笑える瞬間がある。
それが“楽しい野球”の本当の意味じゃないかと思う。
うちのチームは“緩すぎる”
整列してもいつまでも笑ってふざけている。
キャッチボールもノックも、どこか遊びの延長みたいな空気がある。
監督が話している間も私語が止まらない。
試合中に声を出すのは“勝ってるときだけ”。
グラウンドを走る習慣もなく、道具もきれいに並べられない。
叱るのはいつも俺の役目だ。
監督は穏やかで怒鳴ることはない。
だから俺が「締める」側になる。
でも、厳しく言えば言うほど、子どもたちの表情がどこか“やらされてる顔”になる。
その顔を見るたびに、何かが違う気がして、モヤモヤする。
本当の“楽しい野球”って、こんなんじゃない。
そう思いながらも、日々の練習でふざける子どもたちを見て、
心の中で「これが今の時代なのか」と自問してしまう。
“楽しい野球”と“甘い野球”は違う
「楽しくやれ」って言葉は、今の少年野球でよく聞く。
でも、その“楽しく”を“楽(らく)に”と勘違いしてる子が多い。
ヘラヘラ笑ってるだけの練習は、楽しくなんかない。
ミスをしても悔しがらず笑ってるのは、ただの“ぬるさ”だ。
本気で勝ちたいと思って、全力でプレーして、
その先にやっと“楽しい”がある。
本気の中でしか生まれない笑顔がある。
最近は「怒る指導者が悪い」「厳しいのは時代遅れ」なんて言われるけど、
俺はそうは思わない。
怒鳴るのは、勝ちたいからじゃなくて“本気を出してほしい”からだ。
「声を出せ」って言葉の本当の意味は、“気持ちを出せ”なんだ。
でもそれを理解してもらうには、時間がかかる。
何度言っても、ふざけた空気はなかなか抜けない。
仲が良すぎる“甘え”の空気
このチームの6年生は8人。
本当に仲がいい。
それ自体は素晴らしいことなんだけど、同時に一番の課題でもある。
仲が良すぎて、甘えが出る。
ふざけててもみんなで笑って終わる。
厳しく言い合えない。
怒られても「みんなで怒られるから怖くない」。
「アイツもやってないから大丈夫」。
そんな空気がずっとチームに漂っていた。
練習中も試合中も、どこか“なあなあ”で、
誰かが本気を出すと浮いてしまうような雰囲気がある。
俺はその“甘い輪”を壊すために、ずっと戦ってきた。
声を荒げて、厳しく叱って、それでも伝わらない日も多かった。
だけど、やめようと思ったことは一度もない。
なぜなら、心のどこかで「こいつらなら変われる」と信じてたからだ。
本気でやるから、笑える瞬間がある
そんな中でも、時折見せる“本気の顔”がある。
大事な試合、みんながひとつになって全力でプレーした時。
その瞬間のチームは、まるで別人のようだった。
声が自然に出て、ミスしても仲間同士で励まし合って、
一球一球に全員の気持ちが乗っていた。
試合に勝ったあと、ベンチに戻ってきたときの笑顔。
あの笑顔は、ふざけてる時のそれとはまったく違う。
目が違う。
そこにあるのは達成感と誇り。
あの瞬間だけは、全員が“本気で楽しんでいる”顔をしていた。
その笑顔を見ると、怒鳴ったことも悩んだことも、全部報われる。
「これだよ。俺が見たかったのはこの顔なんだ」と、
胸の奥で静かに思う。
“楽しい野球”は、楽な野球じゃない
もうすぐ卒団だけど、結局この1年ずっと“緩さ”と戦ってきた気がする。
最後まで完璧に変わることはなかったけど、
それでも時々見せる“本気の顔”があった。
その一瞬に、すべての意味があると思っている。
“楽しい野球”って、笑ってごまかすことじゃない。
楽をして手に入るものでもない。
本気でぶつかって、悔し涙を流して、
やりきった先にやっと見えるものだ。
指導者も親も、そこを勘違いしちゃいけない。
本気でやった先にある清々しい笑顔こそ、
少年野球の本当の“楽しさ”だと思う。
そして、俺はこれからもあの笑顔を見たい。
叱られても、泣いても、それでも立ち上がる子どもたちの姿を。
それがある限り、俺はきっとまたグラウンドで声を張り上げている。
本気でやることの意味を、チーム運営の視点から見てみると——。
グラウンドから綴る Written on the Field
鬼コーチ
子どもたちには厳しいけれど、本気で成長を願っている「鬼コーチ」です。 怒るのは、技術じゃなく“心”の部分。 教えているつもりが、いつも子どもたちに教えられています。