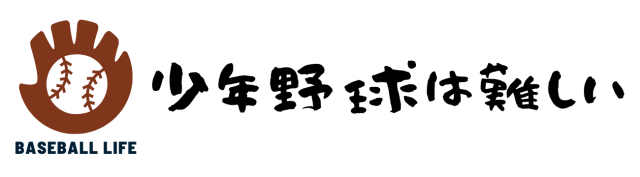「声を出せ!」と怒鳴った日。本当に足りなかったのは何だったのか

「声を出せ!」
少年野球の現場で、一番よく聞く言葉だと思う。
俺もその一人だ。
練習中、試合中、気づけば口から出ている。
でも、あの日——初めて試合中に怒鳴ったあと、
自分でも考えた。「声って、なんなんだ?」と。
試合では怒らないと決めていた
俺は基本、試合中には怒らないと決めている。
試合は子どもたちの舞台。
どんな結果になっても、そこで得られる経験が一番の成長になる。
でも、その日だけは違った。
大事な試合。
中心選手が立て続けにエラーをした。
守備陣は一気に沈黙。
誰も何も言わない。
ベンチから見ていて、空気が凍っていくのが分かった。
まだ負けていない。
逆転されただけだ。
でも、もう“試合を諦めたような空気”が漂っていた。
俺の中で何かがプツンと切れた。
初めて試合中に怒鳴った
気づいたら、立ち上がっていた。
「声出せや! やる気がねぇなら全員引っ込めるぞコラー!!!」
自分でも驚くほどの声量だった。
たぶん、チーム全員が一瞬止まったと思う。
子どもたちの顔に浮かんだのは、怒られたショックよりも“戸惑い”。
“やばい、声出さなきゃ”
そんな空気だった。
俺はその瞬間に、自分の中で「あ、言いすぎたな」と思った。
けど同時に、悔しかった。
まだ試合は終わっていないのに、
この雰囲気のまま負けるのが、何より悔しかった。
子どもたちだって、悔しかったはずだ
冷静になって考えれば分かる。
子どもたちだって、やる気がなかったわけじゃない。
エラーした子も、沈黙した守備陣も、
みんなきっと悔しかったはずだ。
緊張していたかもしれない。
エラーをして申し訳ないという気持ちがあったかもしれない。
でもその時の俺は、
“声が出ない=気持ちがない”と決めつけてしまっていた。
だから、怒鳴るしかなかった。
結果、余計に気持ちは離れた。
本当に伝えたかったこと
少し時間が経ってから、
俺は子どもたちにこう話した。
「エラーをしたやつが声を出さない、それもそうだけど、
周りが声をかけてやれよ。」
自分がエラーしたとき、
チームがシーンとなったらどんな気持ちになる?
「大丈夫!」
「次、取ろう!」
たったそれだけの言葉で、救われることがある。
あの日、俺が本当に言いたかったのはそれだった。
“声を出せ”じゃなくて、“仲間に声をかけろ”だった。
少しずつ変わっていった子どもたち
あの日から、チームの声の出方は変わった。
決して大きな声にはならなかったけど、
ミスをした仲間に声をかけるようになった。
それがすべてだと思う。
「声を出す」って、
単にうるさくすることじゃない。
仲間のために動くこと。
その一歩が“声”なんだ。
そもそも、声ってなんだ?
「声を出せ」って簡単に言うけど、
言われて出す声に意味なんてない。
気持ちがあれば、自然に声は出る。
勝ちたい、負けたくない、助けたい。
その想いが強ければ、声は勝手に出る。
だから“声が出ない”というのは、
気持ちが足りないということ。
でもそれは、子どもたちの責任じゃない。
その気持ちを引き出せていない指導者の責任なんだ。
怒鳴ることの裏にあったもの
あのときの俺は、怒っていたようで、
実は悲しかったんだと思う。
本気でやってきた子どもたちが、
あんなに萎縮している姿を見るのが、ただ悲しかった。
怒鳴って、気持ちをぶつけて、
でも一番足りなかったのは俺の“信頼”。
信頼があれば、怒鳴らなくても伝わる。
信頼がなければ、どんな言葉も届かない。
そう気づいたとき、
俺は自分の未熟さに情けなくなった。
足りなかったのは“声”ではなく“気持ちを繋ぐ力”
あの日、俺は「声を出せ!」と怒鳴った。
でも本当に足りなかったのは、声じゃない。
子どもたちの気持ちを繋ぐ力。
指導者としての“伝える力”だった。
今でも試合中、思い出すことがある。
もしあの時、怒鳴る代わりに
一言「大丈夫、まだ終わってないぞ」と言えていたら、
何か違ったのかもしれない。
でも、あの日の自分も嘘じゃない。
あの後悔があるからこそ、今は怒る前に一呼吸置ける。
“声を出せ”の本当の意味を、
これからも俺は探し続けたいと思う。
指導者としての“怒り”と“優しさ”の間で揺れたことがある人へ。
このテーマも、きっと響くと思う。
グラウンドから綴る Written on the Field
鬼コーチ
子どもたちには厳しいけれど、本気で成長を願っている「鬼コーチ」です。 怒るのは、技術じゃなく“心”の部分。 教えているつもりが、いつも子どもたちに教えられています。